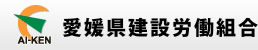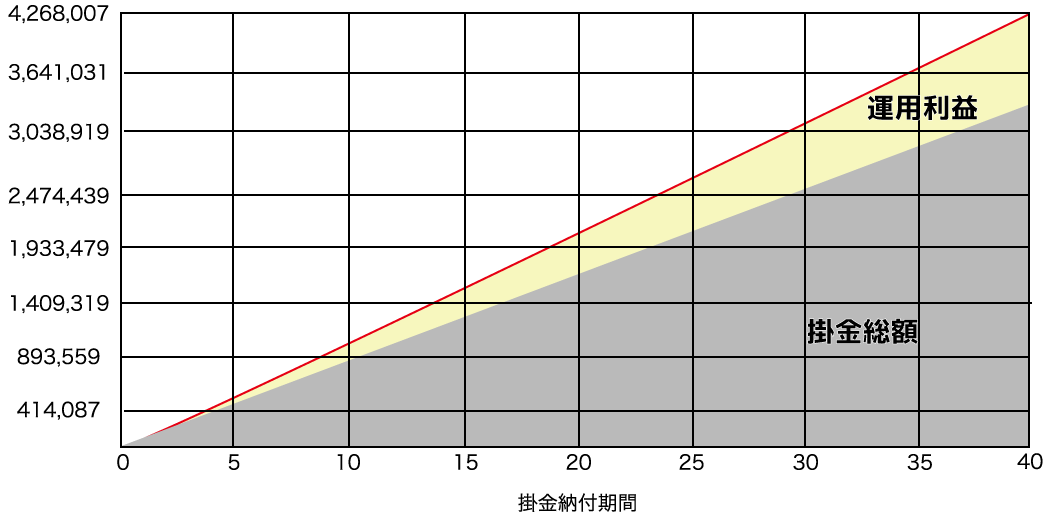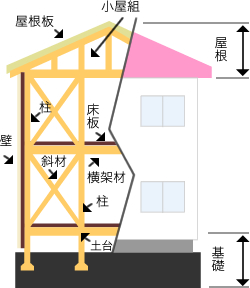中建国保とは
病気やケガなどで仕事に出ることが出来なくなり、収入がなくなってしまう組合員とその家族の生活を支えるための制度です。
加入資格
愛媛県建設労働組合の65歳以下の組合員で、中建国保の規約に基づく職種に従事しており、愛媛県に住民登録していれば加入できます。ただし、建保適用除外事業所に従事しているものは他都道府県に住民登録していても加入できます。
-
医療費は1ヶ月17,500円を超えた支払分が払い戻しされます。※1
- 70歳未満の組合員が1ヶ月(暦の上での1日から31日まで)の中で1つの医療機関で受診した場合、自己負担額が17,500円を超えた分は、払い戻しされます。 ※1 診療内容により、払い戻しにならない場合があります。
-
休業手当は入院1日最高8,000円、通院1日最高4,000円を保障。※2
- 市町村国保にはない「傷病手当金制度」。万が一の時の生活を保障します。※2 病気で連続5日以上労務を休んだとき、1日目から支給。3年を単位として入院・入院外それぞれ50日まで支給します。
-
30歳以下の方は月額医療保険料が低額です。
-
-
20歳未満なら 月額6,800円
-
20歳~24歳なら 月額9,300円
-
25歳~29歳なら 月額11,800円
※いずれも本人のみ加入の場合。
-
-
組合の健康診断はここが違います。
-
-
組合で実施する集団健診は自己負担が発生しません。対象は全ての組合員と中建国保に加入している20歳以上の家族。
-
組合の集団健診の項目は、「がん検診」や「胸部X線検診」などが入ったミニドック検診となっており、労働安全衛生法に基づいた健診項目も全て入っています。
-
専門医による「胸部X線写真の再読影」を無料で受けることができ、じん肺・アスベスト職業病の早期発見ができます。
-
-
指定保養施設の宿泊で、1人1泊につき3,000円を補助。
- 対象施設は全国に約500ヶ所、県内には4ヶ所。家族旅行などに。※施設名、所在地等の詳細は中建国保便利帳をご覧ください。
-
インフルエンザ・肺炎球菌予防接種補助
- インフルエンザ
接種日において資格のあるすべての組合員・家族を対象。接種費用に関わらず、1人あたり2,000円を年度内2回補助します。
肺炎球菌
接種日において資格があり、65歳の誕生日を迎えた組合員・家族が対象。市町村が実施する定期予防接種で接種費用に関わらず、1人あたり2,000円を年度内1回補助します。
-
この他にも・・・
- 介護保険の支給対象となる住宅改修費のうち、介護保険から支給された額と自己負担額(1割分)の合計額を超えた時、超えた額を10万円を限度として補助します。
被保険者の方の健康増進を目的とした「健康体力づくり教室」を開催し、生活習慣病の予防に関する知識の周知を行っています。
-
保険料はどのくらいなの?
-
種別→
被保険者
数↓30歳
以上の
法人
事業主それ
以外の
事業主30歳
以上の
一人
親方30歳
以上の
法人
従業員それ
以外の
従業員25歳
以上
30歳
未満20歳
以上
25歳
未満20歳
未満組合員のみ 33,000 31,200 26,700 22,800 22,100 14,900 12,200 9,600 組合員と家族1人 38,800 37,000 32,500 28,600 27,900 20,700 18,000 15,400 組合員と家族2人 44,600 42,800 38,300 34,400 33,700 26,500 23,800 21,200 組合員と家族3人 50,400 48,600 44,100 40,200 39,500 32,300 29,600 27,000 組合員と家族4人 56,200 54,400 49,900 46,000 45,300 38,100 35,400 32,800 組合員と家族5人以上 62,000 60,200 55,700 51,800 51,100 43,900 41,200 38,600 ※家族は全て23歳以上70歳未満で計算しています。
※介護保険料はふくまれていません。
※後期高齢者支援金分保険料はふくまれています。